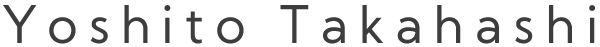Texts List
「絵画」の人 — 高橋淑人(日本語)
勅使河原 純
描くべき対象はすぐそこにある。まるで手を伸ばせば、しっかりと握りしめられる距離だ。だからアーティストは、とりわけ絵描きは、日頃から腕の筋肉を鍛えておかねばならない。腕が自在に動かせるようになったら、今度は手だ。掌を上にして、静かにすべての筋肉を内側に密着させるのがいい。なぜなら、いまから掬いとろうとするのはまこと変幻自在で、厄介この上ない相手だからだ。
——水のように?
いやいや。
——それでは光のように?
だいぶ近い。この世に生を受けたとき、私は最初に光を見、死ぬ時にもまた同じ光に包まれるだろう。真っ暗な闇に光を察知し、目もくらむ光に闇を認めるのだ。この闇は決して恐ろしいだけのものではない。平穏な静寂に満ちていて、私も未だ視ぬものへの記憶に発している心理なのだ。
——未だ視ぬものへの記憶。なんだか印度風ロラン・バルトのようですね。
宇宙だって膨張している。星々がどんどん離ればなれになって、百万光年の孤独に向かって驀信しつつある。だからこそ「絵画」があるのだろう。この世にはどうしたって、てんでんばらばらになるものを、ひとつにまとめていく引力が必要じゃないか。外部へ向かう志向は、内向する意志によって、はじめて釣り合うのだ。大切なのはいつだって両者の微妙な責めぎ合い。
私はつねづね感情や苦悩、不安を超えて、別の精神状態にたどり着きたいと思ってる。絵にはすべてを綜合する不思議な信念が宿っていると思うよ。対象の色とフォルムを粘り強く追いかけていけば、結局はそれがあなた自身につながっているという、身震いするほどの戦慄に逢着するはずだからね。
——表面と裏面の遭遇のような……。絵の具がジワジワっと染みていって、得もいわれぬ深みを生み出す。
そうそう、よく知っているね。西洋からは生みだされない美学だ。彼我一体となった抽象の宇宙だもの。外界と精神の合体には、芸術家しかもち得ない瞑想の「作為」がいる。飽きも懲りもせず、毎日手を修練するなかからはじめて生まれてくる創造上の巧みな工夫だ。私の理解している「作為」とは、作家の精神性と経験上の能力が合体し、それらを通して作家の自我がより高い純粋さへと超越することができる希有な世界なんだよ。
画家はゆったりと、しかし確信に満ちて語り続ける。高橋淑人は一九五四年、東京に生まれた。東京生まれであるからには、あのちょっとばかり寂しい故郷喪失者の一員である可能性がないとはいえない。このめぐり合わせが彼を絵画探究という、まるで現代の修験者のような境遇に追いこんでいったのかもしれない。高橋は恐らく美術大学でまったく迷うことなく、いまではアナクロニズムの典型のように思われている絵画科を選んだのだろう。普通の学生ならば、それはそれで何でもない話である。だが彼の場合は、少しばかり事情が違ったのではなかろうか。作家人生の第一歩で、早くも根本命題にフリーズしてしまった感がある。成績優秀のあまり「絵画」に正直で、その生成の謎に迫ろうとする姿勢が極端に鮮明だったからだ。
メチエ(手技)の限りをつくしながら、いつしかメチエを超えていってしまう絵画という不可解な存在。作為の彼方の見え隠れするゼロ=無作為への止み難いあこがれ。視覚によりながら、平然と視覚を無視してしまう野太さ。目と手との苛酷なまでの対立拮抗。これらはすべて絵画という時代遅れの平面に封じこめられた、解き明かされざる課題なのである。百年ほど前、セザンヌが自然の幾何学的分析を振りまわしたのに対し、高橋の武器は、たとえば二律背反の責めぎ合いであるかもしれない。一九八〇年代、画家はコーティングしたコンクリート板にアクリル絵具を垂らし、和紙で擦りとるというユニークな手法を試みはじめる。このやや迂遠な制作方法が、結果として画家・高橋淑人をとことん鍛え上げていったと私は思う。
紙(画面)の内部へ向かおうとする志向——紙(画面)の外部へはみ出す志向
画家が使う和紙・雲肌麻紙は、実際のところ両面から彩色されていった。意志が反意
志の思わぬ抵抗に遭遇して止揚されていく。「シリーズ 風のしずく work '87-B4」
(一九八七年)などを見ると、一連の神秘な手続きのうちにマクロとミクロの自然
が巧みに掬いとられている。
紙ではなく造形(絵画制作)そのものの内部へと向かう抽象志向——造形(絵画
制作)の外部へ脱出しようとする具象志向
画家の作品はしばしば、岩肌を流れ落ちる水のリアルな表現ともとられてきた。
季節感の指摘などはそのあらわれである。だが「work '92-B1」(一九九二
年)などを見ると、岩肌を流れる水は果たして判りきった具象的光景とい
いきれるのだろうか。
精神の内部へと向かう志向——精神の外部へと刃向かう志向
画家の営みは生活そのものであり、また実生活とかけ離れているといえ
ばおよそこれほど無縁なものもあるまい。これらすべての責めぎ合い。
そこに彼の緊張感を孕んだ芸術のポジションが隠されている。
高橋淑人は一九九一年、アメリカの版画工房ガーナー・ターリスと、日本人としてはじめて契約を結んでいる。ガーナー・ターリスといえば、サム・フランシスやキャサリン・リーが好んで制作した有力工房だ。だだっ広い部屋のワークショップで、金属板による巨大なモノタイプ(エディション一の版画)に挑むチャンスを得た。画面に絵具を押しつけ、根気よく刷りこんでいくだけだった技法が、この辺りから大きな広がりを見せはじめる。例えば刷る行為は、紙を叩く、撫でる、引っ掻く、擦る、磨る、為る、垂らす、振りかける、流す、吹く、飛沫を注ぐ、滴りを飛び散らせる、塗り潰す作業へとスライドしていく。画材はアクリル絵具の他、油絵具、岩絵具、墨、そして陶芸用粘土まで動員されたという。表記としては現代美術らしくミクストメディアだ。
——絵画はどんな効果を追いもとめて制作されるのだろう。
「絵画」には、確かに特有の効果といったものが認められると思う。しかしそれは、デッサンの訓練だけで獲得されるメチエではない。むしろ効果を求めない効果といった方が早いくらいだ。セザンヌがサント=ヴィクトワール山を不思議な分割法で描いて以来、近現代の「絵画」は知覚そのものの研究対象となっている。表面の問題だって新たな地平で議論される可能性がないわけではない。
当たり前のことだが、制作と思考はつねに同時進行していかねばならない。作品はメチエの痕跡であるとともに思考のプロセスともなっている。筆跡へのこだわり、ストロークヘの偏愛、図と地の往還、描き重ねて無に至る「絵画」としての原点にこだわる姿勢。これだけは決して忘れるわけにはいかない。「絵画」は画家にとってさえ、必ずしも安易に近づける世界ではないのだ。
——たいそう思索的ですね。風景は高橋淑人のなかで木霊し、ひとつの身体と人格を得て、自らを語りはじめる。画家はそんな風景の肩をそっと抱き寄せ、客体化し、投影し、和紙の上に投げ出す。あんまり情が深くなると、もう画家と風景ふたりだけの世界だ。他の人にはよく判りませんよ。
だからこそ日々精進しているんじゃあないか。一九九五年以降は版を使うのもやめてしまって、何の変哲もない絵として取り組んでいる。われわれの歴史を縛りつけてきた西洋東洋の区分けをやめ、時間の一方的な流れを踏み越え、心静かに風景(絵画)の成り立ちを尋ねてみたい。難しいことを簡単に説明するのは容易じゃあないし、画家の仕事でもない。そこを何とかつなげてくれる有り難い存在。それこそが、私にとっての「絵画」じゃあないのかな。自分を一生懸命確認していく作業は、まわりまわって結局あなた自身のメッセージであるかもしれないし。画家はこれで、なかなか楽観的な理想主義者でもあるのだよ。恐らくこの話は、これからも途切れることなくつづいていくことだろう。生ある限りはね。
画家との言葉にならないダイアローグは、いよいよ低く静かな情熱を帯びていく。時はもはやギシギシと音をたてて回転するのをやめ、窓辺のトルコ桔梗は花瓶から溢れるようにして、その美しい薄紫を際立たせていた。